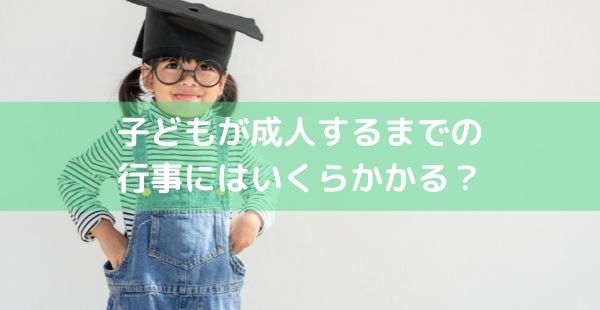子どものお祝い行事の費用や学校への入学費用がいくらかかるかを把握しておくと、前もって準備することができるため突然の出費に慌てることがなくなります。
また、これらの費用を把握しておくことで、ライフイベント表やキャッシュフロー表を作ることが手軽になり、これからの生活を見通すきっかけになるのではないかと考えました。

この記事は次のような人におすすめ!
- 子どものお祝い行事の費用が知りたい人
- 各学校へ入学する際にかかる費用を知りたい人
- ライフイベント表やキャッシュフロー表を作成しようと検討している人
- 行事ごとの費用を把握し、準備しておきたいと思っている人
1.ライフイベント表とキャッシュフロー表
ところで、ライフイベント表やキャッシュフロー表とはどういうものなのでしょう。
家族全員について将来発生する出来事(ライフイベント)を時系列に並べ、表形式でまとめたもの。
現在の収支状況や将来の収入・支出や貯蓄残高を予想し、表形式でまとめたもの。
ライフイベント表やキャッシュフロー表を作成することで、家庭のライフプランが資金面からみて実現可能なのかを判断することができ、また家計の問題点を把握することでその問題を解決するための対策を考えることができます。
2.子どものお祝い行事
お七夜
誕生から七日目の夜に赤ちゃんの成長を願って行うお祝いのこと。
平安時代から続く民族行事で、生まれた子どもに名前をつけて、社会の一員として仲間になることを認めてもらう儀式です。
お七夜は、赤ちゃんの誕生を祝う生まれて最初のお祝い事です。
伝統的には父方の祖父が主催し、親戚などを招いて行われるもののようですが、現在ではその家庭のお祝いしやすいスタイルになりつつあるようです。
お祝いでは、基本的に赤ちゃんの誕生と七日間の生存をお祝いするための「お祝い膳」、名づけをするための「命名書」を用意します。
一般的には、自宅やお店などにそれぞれの両親を招いて行われることが多いようです。
自宅などで行われる場合のお祝い膳は、赤飯と尾頭つきの魚をつけるのが一般的ですが、産後間もないお母さんの体調を考慮して、デリバリーやケータリング、仕出し料理を利用する家庭が多くなっているようです。
- 食事代:5,000円~/一人当たり
お宮参り
子どもが産まれた土地の神(産土神)に子どもが誕生したことを報告し、子どもが無事生まれたことへの感謝と共に、これからの健やかな成長をお祈りする儀式です。
「初宮詣・初宮参り」とも言います。
地方により多少の違いはあるようですが、男の子は生後32日目(または31日目)、女の子は33日目に参詣します。
お宮参りには、以下の費用がかかると考えられます。
- 初穂料(祈祷料):5,000円~1万円
- 衣装代:レンタル 数千円~2万円
購入 2万円~20万円 - 食事代:5,000円~/1人当たり
伝統的には父方の祖父母と行くことが慣習となっていることから、一般的には初穂料などを父方の祖父母が負担することが多いようです。
しかし現代では、両親だけで行う場合や両家で行う場などさまざまですので、その場合は費用は両親が払うのか、父方母方の両家でそれぞれいくら負担するのかを明確にしておく必要がありそうです。
お食い初め
一生食べ物に不自由しないようにとの願いを込め、誕生した子どもに初めて食べ物を与える(真似をする)儀式です。
地域により多少違いがあるようですが、歯が生える生後100日目または120日目に、一生食べ物に不自由することがないようにと念じて食べさせる真似ごとを行います。
伝統的なお食い初めは、一汁三菜の「お祝い膳」を用意します。
内容は、赤飯、汁物、尾頭つきの魚、香の物、紅白の餅、勝栗、歯固め石などです。
お食い初めの費用を負担するのは、一般的に赤ちゃんの両親です。
自宅やお店などに両親や近しい親戚を招いて行います。自宅でお祝い膳を用意する場合の食器ですが、母方の祖父母が家紋入りの食器を用意するのが一般的とされています。
お食い初め膳の宅配もあるようですから、そちらを利用することを検討すると負担にならずに済みますね。
- 食事代:5,000円~/一人当たり
(その他に、自身で新しい食器を用意する場合はその費用)
初誕生
満一歳の誕生日をお祝いする儀式のこと。現在の1年に1度、お誕生日を祝う習慣は欧米から入ってきた文化で、日本にはそれまでそのような慣習はなかったようです。
しかし昔は、満一歳のお誕生日を迎えることが特別なことであったため日本でも一歳の誕生日は盛大にお祝いする風習があったということです。
お祝いでは、地域によって異なるようですが一升餅の儀式と選び取りが一般的に行われます。
一升餅を子どもに背負わせ、子どもの健やかな成長を祈ります。
一升餅を背負えなくても立てなくても喜ばしいこととして受け止めます。
選び取りは子どもの将来を占う儀式。
子どもの前に、そろばんや本、鉛筆、お金、お箸などを並べて子どもが選んだもので将来を占います。
それぞれに意味があり、例えば本を選んだ場合、「学者になる」「博士になる」「頭がよくなる」「成績優秀になる」といった意味があります。
- 一升餅:2,000円~5,000円
- 食事代:5,000円~/1人当たり
(その他に、お餅を入れる風呂敷やリュック、選び取りの道具の用意が必要です。)
初節句
誕生後、初めての節句のことで男の子は5月5日の端午の節句、女の子は3月3日の上巳の節句のことを言います。
初節句は赤ちゃんの無事な成長を祝い、健やかな成長と厄除けを願う儀式です。
雛人形や五月飾り(鎧兜)は、赤ちゃんに降りかかろうとする災厄を、代わりに引き受けてくれる災厄除けの守り神のようなものとされています。
雛人形や五月飾りは母方の祖父母が用意するのが一般的ですが、地域によっては異なるようですし、各家庭によっても異なります。
食事の費用は一般的には子どもの両親が負担しますが、現在では在り方が変化しつつあるため、誰が負担するのかを明確にしておくことが必要です。
- 食事代:5,000円~/1人当たり
(その他に、雛人形や五月飾りを両親が用意する場合はその費用。)
七五三
七歳、五歳、三歳の子どもの成長をお祝いする儀式のこと。
11月15日に神社やお寺などで七五三詣でを行い、子どもの健やかな成長と幸せを祈願します。
七五三の由来は、平安時代にさかのぼり、三歳の「髪置き」、五歳の「袴着」、七歳の「帯解き」の儀式にあると言われています。
七五三の食事に特に決まり事はないようです。
自宅で行う場合はデリバリーやケータリング、仕出し料理を利用する家庭が多くなっているようです。
また、七五三プランという着付けから食事、写真撮影までセットになっているプランを扱うお店もあるようです。
- 初穂料(祈祷料):5,000円~
- 衣装代:レンタル 5,000円~*女の子の衣装の方が若干高めに設定されています
購入 1万円~ - 着付け、ヘアメイク代:3,000円~
- 食事代:5,000円~/1人当たり
成人式
成人式とは、成人式を行う年度内に満20歳を迎える新成人をお祝いする行事。
毎年1月の第二月曜日を成人の日とし、地方自治体の主催により成人式が行われます。
女性は着物、男性はスーツを着用することが多いため費用の内訳の衣装代はこの2つとして考えます。
- 衣装代:着物 レンタル 10万円~(小物を含む)
着物購入 高いものだと100万円超
スーツ購入 2万円~ - 着付け、ヘアメイク:2万円~
- 写真代:2万円~*女性の写真代の方が男性より高めに設定されています
上記のお祝い事の費用負担の説明では伝統的な慣習を載せましたが、地域よって異なることも多く、また現代では在り方が変化してきているため、このお祝い事の費用は父方、または母方が払わなくてはならないということはありません。
伝統にとらわれず両親、両家の祖父母が納得する形で行うのが一番です。
3.幼稚園から大学までの初年度納付金
下記は公立学校、私立学校の初年度納付金の表です。
令和元年10月から幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料は基本的に無料になっています。
また、高等学校への進学率が98%であるという現状から、高等学校等就学支援金制度が制定されています。
公立高校に通う生徒には年間11万8,800円の支給で実質無料となっており、私立高校に通う生徒に対しても令和2年4月より制度の改正で支援が厚くなりました。
| 進学過程 | 公立・国立 | 私立 |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 12,700円 | 414,000円 |
| 小学校 | 12,200円 | 852,000円 |
| 中学校 | 16,700円 | 807,000円 |
| 高等学校 | 55,300円 | 748,000円 |
| 専門学校 | 1,255,000円 | 1,255,000円 |
| 大学 | 817,000円 | 1,340,000円 |
*専門学校については私立の専門学校のデータであり、初年度の入学金、授業料、実習費、設備費、その他の合計金額(令和2年度調査)
*私立大学については初年度の授業料、入学料、施設整備料等の合計金額(令和2年度調査)
*国立大学については初年度の授業料、入学料の合計金額(令和元年度調査)
参考資料:国公私立大学の授業料の推移
4.お祝い金の相場は?
子どものお祝い行事では、父方、母方の祖父母や親戚、あるいは友人からお祝いを頂く機会があります。
お祝い金の金額に特に決まりはありませんが、3,000円~数万円と考えておいてよいでしょう。
お祝いを頂いたら内祝いを忘れずに。
金額の目安は、頂いたお祝いの半額~3分の1程度が基本です。
5.まとめ
- 子どものお祝い行事では、特に食事代に費用がかかります。
また、七五三や成人式では衣装代にも費用がかかってきます。 - お祝い行事にかかる費用の負担は誰がするのかを、父方、母方の祖父母などと相談しましょう。
- 幼稚園から大学までの初年度納付金は、計画的に準備しておくと安心です。
Text:Yuri Ishiguro
Director:Hirotaka Dezawa